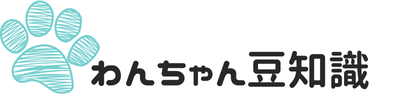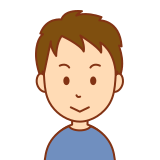
飼い主さん
うちの子、なんだか臭うなぁ・・・
愛犬の匂いは、飼い主さんにとって一番身近で気になるお悩みのひとつですよね。
わんちゃんの体臭は、単なる「犬臭い」で片付けられない、健康状態のバロメーターでもあります。
匂いの原因を特定し、正しい対策をすることで、愛犬の健康を守り、私たち人間も快適に過ごせるようになります。
この記事では、体臭を4つのタイプに分け、それぞれの原因と、いますぐできる具体的な対処法を詳しくご紹介します。
愛犬の体臭を4つのタイプでチェック!
体臭は、発生源や原因によって匂いの種類が異なります。
愛犬の体臭がどのタイプに近いかチェックし、原因を絞り込みましょう。
| 匂いのタイプ | 臭いの特徴 | 発生源として多い部位 |
| 1. 脂っぽい・酸っぱい臭い | 油が酸化したような、または酸味のある不快な臭い。 | 耳の中、脇の下、内股、皮膚全体。 |
| 2. 生臭い・腐敗臭 | 魚や生ごみのような、非常にきつい生臭い臭い。 | 口(歯)、肛門腺、皮膚の傷口。 |
| 3. カビっぽい・酵母臭 | パン生地や醤油のような、少し甘くカビっぽい独特の臭い。 | 耳の中、皮膚のしわ(ブルドッグ、パグなど)。 |
| 4. おしっこ・アンモニア臭 | ツンとする刺激臭や、おしっこが濃いような臭い。 | 被毛全体、口。 |
タイプ別!気になる臭いの根本原因と対策!
体臭のタイプごとに、具体的な原因と自宅でできる初期対処法を見ていきましょう。
脂っぽい・酸っぱい臭い(原因:皮脂の過剰分泌、細菌の増殖)
【根本原因】
- マラセチア皮膚炎:皮膚の常在菌であるマラセチア(酵母菌)が、皮脂の過剰分泌により異常増殖した状態。ベタベタしたフケや赤みを伴うことが多いです。
- 体質・季節:もともと皮脂腺が多い犬種(柴犬など)や、高温多湿の夏場に、皮脂が過剰に出て酸化してしまう。
【対処法】
- シャンプーの見直し:皮脂をしっかりと洗い流す脱脂力の高いシャンプーを使用し、獣医師と相談して薬用シャンプーを取り入れる。
- 乾燥対策:シャンプー後はしっかりと乾かし、湿度が高すぎない環境を保つ。
生臭い・腐敗臭(原因:口腔疾患、肛門腺、細菌感染)
【根本原因】
- 歯周病・歯石:口の中に溜まった歯垢や歯石で細菌が増殖し、腐敗臭を放っている(最も多い原因)。
- 肛門腺の蓄積:肛門の両脇にある袋(肛門腺)に分泌液が溜まりすぎ、排出されずに腐敗臭を放っている。
- 外耳炎:耳の中に細菌や真菌が繁殖し、きつい生臭い臭いを放つ。
【対処法】
- 口臭対策:毎日の歯磨きを徹底する。歯石がついていたら、動物病院で歯石除去(スケーリング)を検討する。
- 肛門腺絞り:トリミング時や自宅で肛門腺絞りを行う。頻繁に溜まる場合は、獣医師やトリマーに相談しましょう。
カビっぽい・酵母臭(原因:マラセチア、アレルギー)
【根本原因】
- アレルギー性皮膚炎:アレルギーによって皮膚のバリア機能が低下し、マラセチア菌などが二次的に増殖している状態。
- 耳の通気性不良:垂れ耳の犬種(コッカー・スパニエルなど)や、皮膚にシワが多い犬種(ブルドッグ、パグなど)は、通気性が悪くマラセチアやカビ菌が繁殖しやすい。
【対処法】
- 耳の掃除:獣医師に教わった方法で、週に一度を目安に犬用のイヤークリーナーで優しく耳掃除をする。
- シワのケア:顔のシワや内股など、皮膚が重なっている部分を、濡れたタオルやウェットティッシュで拭き、乾燥させる。
- アレルギー検査:臭いが慢性化している場合は、根本原因であるアレルギー検査を検討する。
おしっこ・アンモニア臭(原因:腎臓・代謝機能の低下)
【根本原因】
- 腎臓病:腎臓機能が低下すると、体内のアンモニアなどの老廃物をうまく尿として排泄できず、口臭や体臭としてアンモニア臭がすることがあります(非常に危険なサイン)。
- 被毛の汚れ:排泄後の処理が不十分で、おしっこや便が被毛に残っている。
【対処法】
- 獣医師の診察:アンモニア臭がする場合は、迷わず動物病院を受診し、血液検査などで腎臓の機能を確認してもらいましょう。
- 被毛の洗浄:排泄後のお尻周りをこまめに拭く、または部分的にカットして汚れが付きにくいようにする。
体臭を根本から断つための日常ケア!
単なる「洗浄」で終わらせず、体の中から臭いの発生を防ぐための具体的なケアを実践しましょう。
腸内環境を整える
皮膚や体臭は、腸内環境と密接に関わっています。
- 乳酸菌・サプリメント:腸内の悪玉菌の増殖を抑え、体臭の原因となる老廃物の排出をサポートする犬用の乳酸菌や整腸剤を取り入れる。
- 食事の見直し:消化に良い良質なフードを選び、不要な添加物や脂質が過多な食事を控える。
シャンプー後の「完全乾燥」を徹底
濡れた被毛を放置すると、雑菌やカビ菌が繁殖する絶好の環境になってしまいます。
- ドライヤーの徹底:特に毛量が多い犬種や、毛の長い犬種は、根元まで完全に乾かすことが必須です。生乾きは臭いの原因になります。
- 通気性の良いブラシ:ブラッシングの際に、通気性の良いブラシで毛の根元に風を通しながら乾かすと効率的です。
被毛の「通気性」を意識したブラッシング
- 毎日のブラッシング:ブラッシングは、抜け毛を取り除き、皮膚の通気性を保つために重要です。
抜け毛を放置すると、湿気がこもり、皮膚病や臭いの原因になります。 - 換毛期の対策:換毛期には、特に念入りにブラッシングを行い、死毛(抜け落ちた毛)を徹底的に取り除きましょう。
まとめ:愛犬の匂いを消すための3つの行動!

| 項目 | 臭いのタイプ別対応 | 飼い主ができる最善の対策 |
| 初期チェック | 酸っぱい臭い(皮脂)、生臭い(口・肛門腺)、アンモニア臭(腎臓)。 | 臭いのタイプを特定し、緊急性の高い腎臓病や歯周病のサインを見逃さない。 |
| 外部ケア | 雑菌の繁殖を防ぐ。 | シャンプー後は根元まで完全乾燥させる。垂れ耳やシワの部分は通気性を確保する。 |
| 体内ケア | 腸内環境と代謝。 | 乳酸菌や整腸剤で腸内環境を整え、アンモニア臭がする場合は獣医師の診察を最優先する。 |
愛犬の臭いが気になったら、「どこが臭いか」「どんな臭いか」を冷静に観察することが、健康を守る第一歩です。
日々のこまめなケアと定期的な健康チェックで、臭いのない快適な生活を手に入れましょう!
我が家の愛犬はミニチュアシュナウザーで、外耳炎になりやすい犬種らしく本当に頻繁になりました。
きつい生臭い臭いがして、ひどいときは首を傾けたまま動けなくなることもありました。
耳を気にする行動があれば、早く動物病院に行き早く治療してあげてね。
早く気付いてあげれれば早く治りますよ。