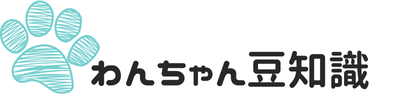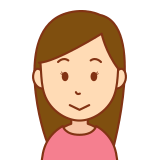
来客のたびに、吠え続ける・・
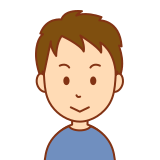
散歩中にすれ違うわんちゃんに、激しく吠える・・
愛犬の「無駄吠え」は、集合住宅でのトラブルや、飼い主さんの精神的な負担に繋がりかねない深刻な悩みです。
しかし、わんちゃんにとって「吠える」のは大切なコミュニケーション手段であり、異常な行動ではありません。
私たち人間が「無駄だ」と感じる吠えのほとんどは、不安、要求、警戒といった、愛犬からの切実なメッセージなのです。
大切なのは、「なぜ吠えているのか?」という根本原因を特定し、その原因に応じた正しい方法で「吠えなくても大丈夫」「吠えなくても要求が通る」と教えることです。
この記事では、無駄吠えの主要な4つの原因を特定し、それぞれの原因に対する具体的な行動修正のしつけ方と、飼い主さんが絶対にやってはいけないNG行動を徹底解説します。
愛犬の吠えはどのタイプ?「4つの原因」
無駄吠えの原因は多岐にわたりますが、ここでは最も一般的な4つのタイプに分類し、それぞれの対処法を考えます。
| 吠えのタイプ | 特徴的な状況とサイン | わんちゃんの心理(原因) |
| 1. 要求吠え | 飼い主に対して、おもちゃ、おやつ、散歩、構ってほしい時などに吠える。吠えると要求が通ることを知っている。 | 「これをすればもらえる・通る」という学習による行動。 |
| 2. 警戒・威嚇吠え | 来客、訪問者、インターホン、外の音、散歩中の人や犬など、「縄張りを侵す者」や「怖いもの」に対して吠える。唸り声や低い声が混じる。 | 「縄張りを守ろう」「怖いから近づくな」という防衛本能。 |
| 3. 不安・分離不安吠え | 飼い主が視界から消えた時、留守番中、夜間などに、クーンという鳴き声が混じった、切羽詰まった声で吠え続ける。 | 「不安でパニック」「一人にしないで」という強い依存心と恐怖。 |
| 4. 興奮・遊び吠え | 遊びの最中、散歩の直前、飼い主が帰宅した時など、喜びや興奮が高まった時に甲高く吠える。 | 「嬉しい!」「早くしたい!」という感情の高まり。 |
原因別!無駄吠えの「行動修正トレーニング」
原因によって、しつけ方は全く異なります。叱る前に、愛犬の心を満たす正しいアプローチを行いましょう。
対策①:要求吠え — 「無視の徹底」と「先回り」
要求吠えは、わんちゃんが主導権を握っている状態です。
「吠えれば要求が通る」という成功体験を徹底的にリセットします。
- 徹底した無視: 吠えている間は、絶対に、アイコンタクトも声かけもせず、完全に無視します。
おやつや、構う要求が一切通らないことを学習させます。 - 吠え止んだ瞬間を褒める: わんちゃんが一瞬でも吠えるのを止めて、落ち着いたら、すぐに大げさに褒めて要求を満たしてあげます。
- 「先回り」で要求を満たす: 吠える前に「おすわり」や「フセ」などの指示を出し、落ち着いた状態で要求を満たしてあげます。
「吠える前に指示に従うと良いことがある」と学習させます。
対策②:警戒・威嚇吠え — 「安全距離」からの慣れ
警戒吠えは不安や恐怖から来るため、叱ってはいけません。
「吠えなくて大丈夫」と安心させてあげる環境調整が必須です。
- 安全距離(しきい値)を見つける: わんちゃんが警戒心を持ちつつも、まだ吠え出さない距離(例えば、来客から5メートル離れた場所)を見つけます。
これを「安全距離」とします。 - 安全距離でのポジティブ経験: 安全距離で警戒対象(人、インターホン、他のわんちゃんなど)を見せている間だけ、最高に美味しいおやつを与えます。
- 例: インターホンの音が鳴る直前におやつを渡し、鳴っている間も与え続ける。
- 距離を徐々に詰める: 吠えずにいられたら、次のセッションで少しずつ警戒対象との距離を縮めていきます。
「警戒対象=美味しいものがもらえるサイン」に書き換えます。 - 環境管理: 玄関や窓からの視界を遮断するために、カーテンや目隠しシートを使い、不必要な警戒の機会を減らします。
対策③:不安・分離不安吠え — 「依存心の解消」
ステップ1で解説した留守番トレーニングと同じく、飼い主への過度な依存を解消する必要があります。
- 安全基地の確立: クレートやサークルを最も落ち着ける場所とし、日常的に使用します。
- 短時間の分離練習: わんちゃんが落ち着いているときに、1秒、3秒とごく短時間だけ、
わんちゃんの視界から消える練習を繰り返し、「離れても必ず戻ってくる」という信頼を構築します。 - クールな対応: 出かける時も帰宅した時も、大げさな挨拶やスキンシップは避け、クールに接することで、依存心を助長させないようにします。
対策④:興奮・遊び吠え — 「落ち着き」の学習
興奮した状態から、冷静な状態へスムーズに戻れるようにトレーニングします。
- クールダウンの強制: 遊びの最中や散歩の準備中に吠え始めたら、その瞬間に遊びや準備を中断し、無視します。
- 「落ち着き」を教える: 吠え止んで、座るか横になるなど落ち着いた行動を見せたら、すぐに遊びを再開したり、散歩に連れ出したりします。
- 静かな行動に報酬を与える: 興奮のピークが来る前に、「フセ」や「マテ」などのコマンドで落ち着かせる習慣をつけ、それができたらご褒美を与えます。
無駄吠え対策で、絶対にやってはいけない「NG行動」
無駄吠えのしつけで失敗する多くのケースは、以下のNG行動によって、かえって吠えを悪化させていることにあります。
| NG行動 | 悪影響(なぜダメなのか) | 代替すべき行動 |
| 1. 吠えた時に大声で「ダメ!」「静かに!」と叱る | わんちゃんは、飼い主も一緒に「吠えてくれている」「構ってくれている」と勘違いし、吠えを強化してしまう。 | 無言・無表情で無視し、興奮させない。 |
| 2. マズル(口元)を押さえる | わんちゃんは、身動きを封じられることで恐怖心と不信感を抱き、かえって次の吠えが激しくなる(特に警戒吠え)。 | 吠える原因(刺激)から距離を取り、安心させる。 |
| 3. 吠え続ける愛犬を抱きしめる(不安吠え) | 飼い主が抱きしめることで、「吠えるほど不安になれば、飼い主が来てくれる」という行動を強化してしまう。 | 落ち着いた瞬間まで待ち、その時に穏やかに声をかける。 |
| 4. 最終手段として叩く・体罰を与える | わんちゃんとの信頼関係が崩壊し、問題行動がさらに複雑化するだけでなく、恐怖から噛みつきなどの攻撃性を引き起こす危険がある。 | ポジティブ・トレーニング(ご褒美を使う方法)で行動を修正する。 |
まとめ:無駄吠え対策の「3つの鉄則」

| 鉄則 | 対策の目的 | 飼い主が守るべき行動 |
| 1. 原因特定 | 吠えは「要求」「警戒」「不安」など、愛犬からのメッセージだと理解する。 | 愛犬の吠えを4つのタイプに分類し、適切なアプローチを見極める。 |
| 2. 無視の徹底 | 要求吠えや興奮吠えの「成功体験」をゼロにする。 | 吠えている間は、声かけ、アイコンタクト、接触を完全に絶つ。 |
| 3. 環境の調整 | 警戒吠えや不安吠えのストレスの原因を取り除く。 | 警戒対象から安全距離を取り、視界を遮断する。吠える直前にご褒美を与えて不安を解消する。 |
無駄吠えのしつけは、すぐに結果が出るものではありません。
根気よく一貫した対応を続けることが重要です。
愛犬を叱るのではなく、「どうすれば吠えずに済むか」という視点に立って、愛犬の気持ちに寄り添いながらトレーニングを進めていきましょう。