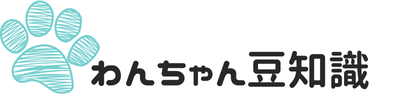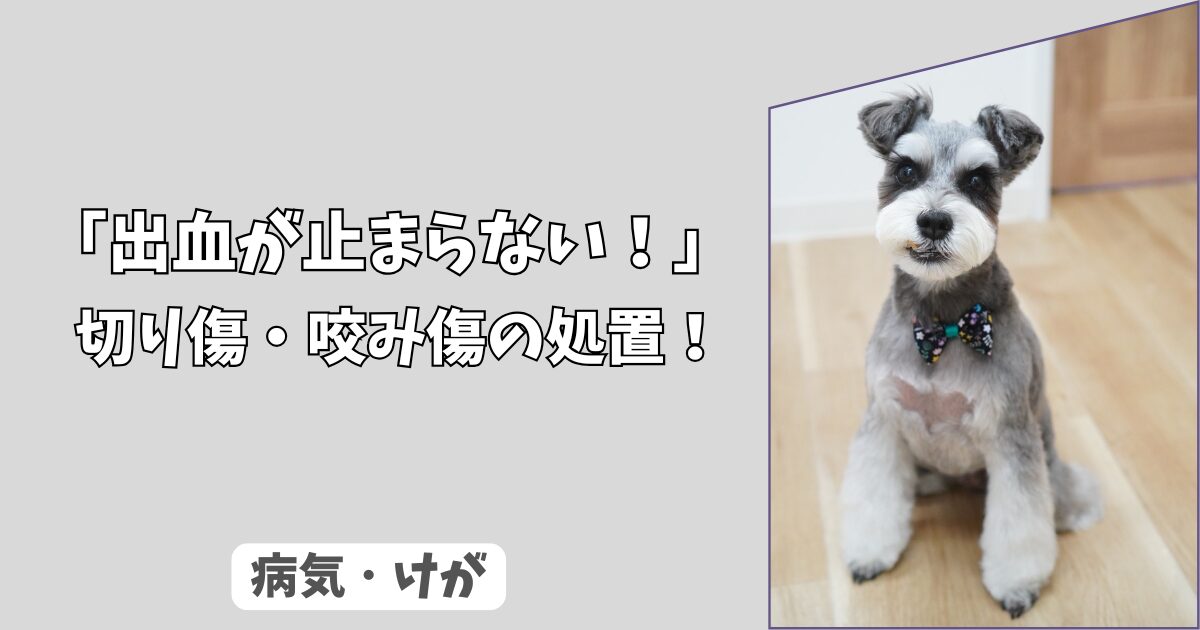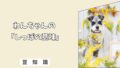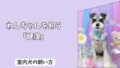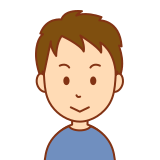
飼い主さん
散歩中に大きな切り傷を作ってしまった!
どうすればいい?
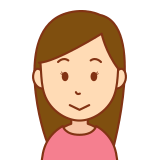
飼い主さん
他のわんちゃんに噛まれたけど、
昔の消毒液で消毒してもいいの?
愛犬が怪我をして出血している現場に遭遇すると、飼い主さんはパニックになりがちです。
しかし、出血時は「迅速な止血」と「正しい応急処置」が、愛犬の命を守り、傷の治りを左右する重要な鍵となります。
特に、わんちゃん同士の咬み傷は、見た目以上に深く、重篤な感染症を引き起こすリスクが高いため、注意が必要です。
また、人間が使う消毒液の多くは、わんちゃんの傷の治癒を妨げ、痛みを増強させる可能性があるため、使い方には最新の注意が必要です。
この記事では、愛犬が怪我をした際の「止血の3原則」を具体的に解説します。
次に、傷の種類別のリスクを知り、なぜ多くの消毒がNGなのかという科学的な理由を解き明かします。
そして、適切な処置を施した後、いつ動物病院に連れて行くべきかという判断基準までを徹底解説します。
出血を止める「止血の3原則」(緊急時)
愛犬が怪我をして出血した場合、まず飼い主さんがパニックにならず、以下の手順で止血を行うことが最優先です。
清潔なもので「圧迫」する(最も重要)
- 目的: 血管を物理的に圧迫し、血液の流出を止める。
- 方法: 清潔なガーゼ、タオル、ハンカチなどを準備します。出血している傷口の上にこれらを厚めに当て、数分間、強く、一定の力で圧迫し続けます。
- 注意点: 途中で出血状況を確認するために圧迫を緩めないこと。
圧迫しているガーゼが血でいっぱいになっても、新しいガーゼを上から重ねて圧迫を続けます。
患部を「心臓より高く」保つ
- 目的: 重力の作用で、傷口への血流を減少させる。
- 方法: 怪我をした場所が四肢(手足)の場合、可能であれば、愛犬を横に寝かせ、傷のある足を心臓の位置よりも高く持ち上げます。
- 注意点: 愛犬が痛がったり嫌がったりして、飼い主が噛まれるリスクがある場合は、無理せず圧迫止血を優先します。
止血後、清潔な「保護材」で覆う
- 目的: 傷口を保護し、細菌感染を防ぐ。
- 方法: 出血が止まったら、傷口を再度刺激しないよう注意しながら、清潔なガーゼや包帯で優しく覆い、固定します。
この保護は、病院に到着するまでの間、傷口を清潔に保つために重要です。
傷の種類別「隠れたリスク」と判断基準!
傷の種類によって、見た目以上に深刻なリスクが潜んでいることがあります。
切り傷・擦り傷
- リスク: 傷が浅ければ家庭で応急処置が可能ですが、深い切り傷は血管や腱、筋肉を損傷している可能性があります。
- 病院へ行くべき目安:
- 圧迫止血を10分続けても血が止まらない。
- 傷口がパックリ開いており、縫合が必要だと判断される。
- 傷口の深さが皮膚の下の脂肪や筋肉まで達している。
咬み傷(わんちゃん同士の喧嘩など)
- リスク: 咬み傷は、見た目の傷口が小さくても、わんちゃんの牙によって皮膚の下の組織が深く裂け、細菌が奥深くまで運ばれているケースが非常に多いです(パンク傷)。
- 最重要事項: 咬み傷は、出血が少なくても必ず動物病院を受診してください。
皮膚の下で感染が進み、数日後に膿が溜まって高熱が出るなど、重篤な状態になることがあります。
治療には抗生物質の投与が必要となるケースがほとんどです。
消毒液が「NG」な理由と正しい処置!
人間が軽度の傷に使う消毒液の多くは、愛犬の傷の治癒を妨げたり、痛みを引き起こしたりする
ため、推奨されません。
消毒液が、NGな科学的理由
- 細胞へのダメージ: 多くの消毒液(特にアルコール系や刺激の強いもの)は、傷口の細菌を殺すのと同時に、傷を治そうとしている健康な細胞(線維芽細胞など)までも破壊してしまいます。
これにより、傷の治りが遅れたり、皮膚の再生がうまくいかなくなったりします。 - 痛みとショック: 強い刺激が愛犬に激しい痛みを与え、トラウマになったり、治療を嫌がったりする原因になります。
正しい洗浄と処置
- 洗浄の原則: 傷口の異物や汚れを洗い流すことが重要です。
使用するのは、生理食塩水が最適ですが、緊急時は清潔な流水(水道水)を優しくかけて洗い流します。 - 塗り薬の自己判断はNG: 人間用の塗り薬や軟膏は、わんちゃんが舐めてしまうと中毒を起こしたり、皮膚炎を悪化させたりする可能性があるため、獣医師の指示なく使用しないでください。
- エリザベスカラーの装着: 病院に行くまでの間、愛犬が傷口を舐めたり噛んだりしないよう、エリザベスカラーやTシャツなどで保護することが有効です。
病院へ連れて行く時の注意点!
止血と応急処置が完了したら、愛犬の安全に配慮しながら病院へ向かいます。
鎮静と保温
- 鎮静: 愛犬は痛みとショックで興奮している可能性があります。
優しく声をかけ、体を清潔なタオルで包んで安心させます。 - 保温: 大量出血やショック状態にある場合は、体温が低下している可能性があります。
タオルや毛布で体を包み、保温に努めましょう。
情報の伝達
- 事前に連絡: 病院へ向かう前に必ず電話で連絡を入れ、「怪我の状況(切り傷か咬み傷か)」「出血の有無」「応急処置の内容」を伝えましょう。
病院側が迅速に受け入れ準備をすることができます。 - 出血量: 出血量がわかるよう、使用したガーゼやタオルを持参するか、出血の程度を具体的に伝えられるようにしておくと、診察がスムーズに進みます。
まとめ:止血と処置の「命を守る3原則」

| 処置の原則 | 緊急時の最優先事項 | 病院へ行くべきサイン |
| 止血 | 清潔なガーゼで強く圧迫し心臓より高く保つ。 | 10分間圧迫しても止まらない出血。 |
| 洗浄 | 水道水や生理食塩水で優しく汚れを洗い流す。 | 傷口がパックリ開いている、深さがある。 |
| 消毒 | 刺激の強い消毒液は使わない。健康な細胞を破壊する。 | 咬み傷(出血が少なくても)、発熱など感染の兆候。 |
愛犬の怪我への対応は、一瞬の判断と行動が重要です。
この記事で学んだ知識を活かし、愛犬の安全を守るための正確な応急処置を実践し、
速やかに獣医師の診断を受けましょうね。