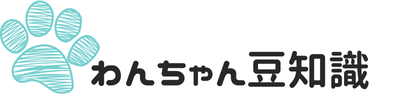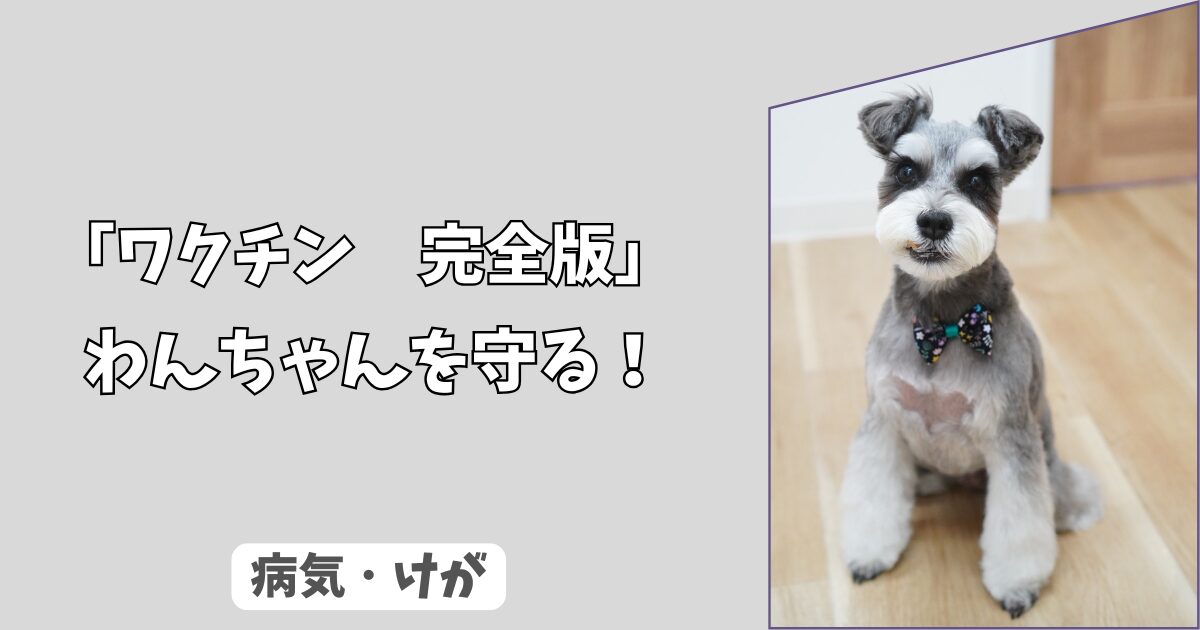新しい家族である子犬を迎えたら、まず考えなければならないのが「ワクチン接種」です。

いつから打つの?
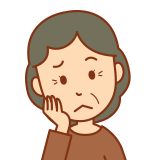
種類がたくさんあって、何を打てばいいの?
ワクチンは、愛犬を致死率の高い恐ろしい感染症から守る「命の盾」です。
正しい知識とスケジュールで接種することで、愛犬を病気から守り、安心してドッグランや他のわんちゃんとの交流を楽しめるようになります。
この記事では、愛犬のワクチン接種について、「法律で定められた必須ワクチン」から「命を守る混合ワクチン」まで、子犬からシニア犬までの完全なスケジュールと注意点を詳しく解説します。
知っておきたい!ワクチンの2大種類と役割!
わんちゃんのワクチンは、大きく分けて「狂犬病ワクチン」と「混合ワクチン」の2種類があります。
それぞれ役割と接種時期が異なります。
| ワクチンの種類 | 義務/任意 | 目的と特徴 | 接種時期 |
| 狂犬病ワクチン | 法律で接種が義務 | 狂犬病(発症するとほぼ100%死亡)の予防。 | 生後91日以降(毎年1回)。 |
| 混合ワクチン | 任意(強く推奨) | ジステンパー、パルボウイルスなど、致死率の高い伝染病をまとめて予防。 | 子犬期に複数回、成犬期は1〜3年に1回。 |
狂犬病ワクチン(法律で義務)
狂犬病は、わんちゃんだけでなく人間にも感染する恐ろしい病気です。
日本での発生は稀ですが、一度発症すると有効な治療法がなく、ほぼ100%死亡します。
そのため、法律により生後91日以上のわんちゃんは毎年1回の接種が義務付けられています。
混合ワクチン(命を守る任意接種)
混合ワクチンは、一回の注射で複数の感染症を同時に予防します。
「コアワクチン」と呼ばれる致死率の高い病気(ジステンパー、パルボ、アデノウイルスなど)の予防が中心です。
- 何種混合を選ぶか? 5種、8種、10種などがありますが、生活環境(ドッグラン利用頻度、キャンプに行くかなど)によって接種すべき種類が変わります。
獣医師と相談して選びましょう。
子犬のための「最強スケジュール」
子犬の時期は、ワクチン接種が最も複雑で重要です。
なぜ複数回打つ必要があるのか、その理由とスケジュールを見ていきましょう。
なぜ複数回打つ必要があるの?(移行抗体の影響)
生まれたばかりの子犬は、母犬の母乳(初乳)から「移行抗体」という免疫をもらっています。
この抗体が体内に残っている間は、ワクチンを接種しても効果が打ち消されてしまうのです。
- 移行抗体が切れる時期には個体差があるため、確実に免疫をつけられるよう、2〜3回に分けて接種します。
これが子犬期に複数回接種が必要な理由です。
標準的な子犬の接種スケジュール
| 接種回数 | 目安となる月齢 | 接種するワクチンの種類 | 重要なポイント |
| 1回目 | 生後45〜60日頃 | 混合ワクチン | 移行抗体が残っている可能性がある。 |
| 2回目 | 生後90日前後 | 混合ワクチン | 1回目から3〜4週間後。多くの移行抗体が切れる時期。 |
| 狂犬病 | 生後91日以降 | 狂犬病ワクチン | 混合ワクチンの最終接種後、1ヶ月以上空けて接種する。 |
| 3回目(最終) | 生後120日以降 | 混合ワクチン | 2回目から3〜4週間後。確実に免疫をつけるための最終接種。 |
社会化期を逃さないために
子犬の「社会化期」(生後3〜4ヶ月頃)は、外の世界に慣れるために非常に大切な時期です。
しかし、ワクチンの免疫が完成するまでは、外での接触を控える必要があります。
- 外出OKの目安: 混合ワクチンの最終接種から約1〜2週間後に免疫が完成するとされています。
それまでは、散歩は抱っこで、他のわんちゃんとの接触は避けましょう。
成犬・シニア犬の接種計画!
子犬期に免疫をつけた後も、ワクチンの効果は徐々に薄れていきます。
毎年の接種は本当に必要?
混合ワクチンは、現在「1年に1回」または「3年に1回」の接種が推奨されています。
- 1年接種(ノンコアワクチン): レプトスピラ症など、効果の持続期間が短いワクチンが含まれている場合、毎年接種が必要です。
- 3年接種(コアワクチン): ジステンパーなど、効果の持続期間が長いコアワクチンのみを接種する場合。
- 獣医師と相談: 愛犬の生活環境(河川敷で遊ぶか、他の犬との接触頻度など)に応じて、毎年打つべきか、3年に一度で済むか、獣医師と相談して決めましょう。
注目される「抗体価検査」という選択肢
近年、「抗体価検査(こうたいかけんさ)」という、体内の抗体が十分に残っているかを調べる検査が注目されています。
- メリット: ワクチン接種による体への負担(副反応)を避けつつ、免疫が残っているかを確認できる。
- デメリット: 検査費用がかかる。狂犬病ワクチンには適用できない。
ワクチン接種の「安全マニュアル」
ワクチン接種を安全に行うために、以下の点に注意しましょう。
接種前の最終チェック
- 体調が万全か? 下痢、咳、元気がない、発熱などの体調不良がある場合は、必ず接種を延期してください。
- 狂犬病と混合ワクチンは1ヶ月空ける: 体への負担を減らすため、原則として両ワクチンは最低1ヶ月の間隔を空けて接種します。
接種後の「安全な過ごし方」
- 安静を徹底: 接種当日は、散歩、激しい運動、シャンプーは控え、家でゆっくり休ませます。
- 副反応の観察: 接種後30分は、顔の腫れ、呼吸困難、ぐったりなどの重篤な副反応が起きやすい時間帯です。
可能であれば、病院の近くで様子を見てください。
まとめ:愛犬の未来を守るための3つのステップ!

| 項目 | 愛犬の安全を守るために | 飼い主ができる最善の行動 |
| 基本知識 | 狂犬病は毎年義務、混合ワクチンは重い感染症予防。 | どちらのワクチンも間隔を1ヶ月以上空けて接種スケジュールを立てる。 |
| 子犬期 | 移行抗体があるため複数回接種が必要。 | 最終接種後、1〜2週間は他の犬との接触を避ける(免疫完成待ち)。 |
| 成犬期 | 1年または3年に1回の混合接種を検討。 | 生活環境と相談し、抗体価検査も選択肢に入れながら、獣医師と相談して決める。 |
ワクチン接種は、愛犬に贈る最初の、そして最も大切な健康へのプレゼントです。
正しい知識を持って、愛犬の健康を生涯にわたって守ってあげましょう!
混合ワクチンには、5種や8種などありますが「多い種類を打ってれば安心」などと思わないで下さい。
体に異物(ワクチン)を入れると言う事は、何らかの副作用があるはずです。
生活環境に合わせた混合ワクチンをしっかり選んであげて下さい。